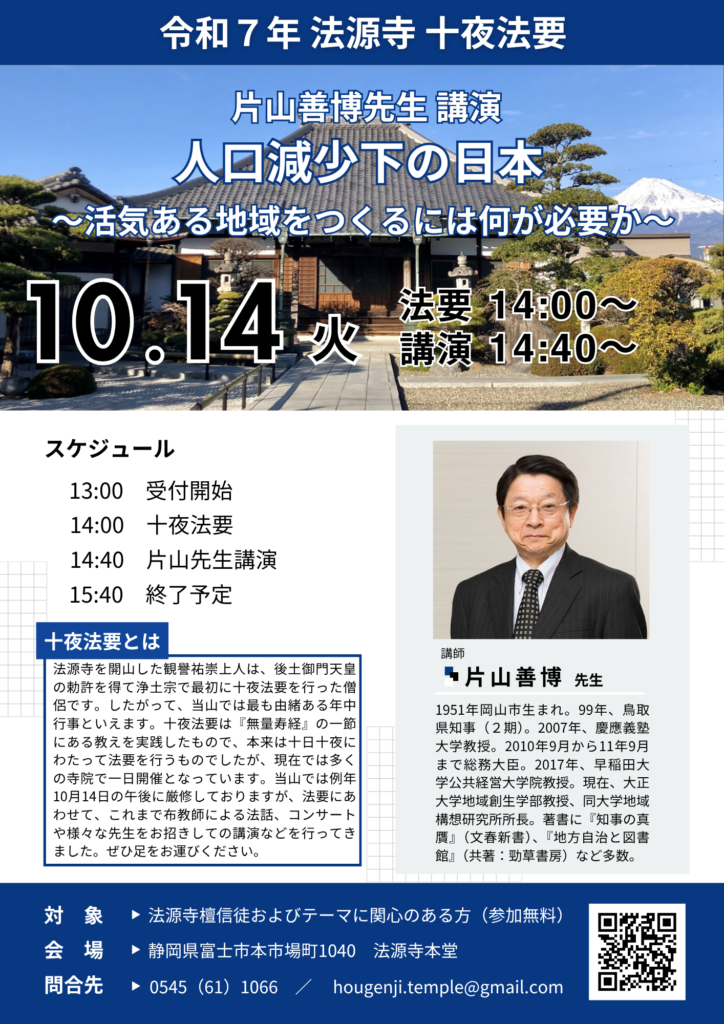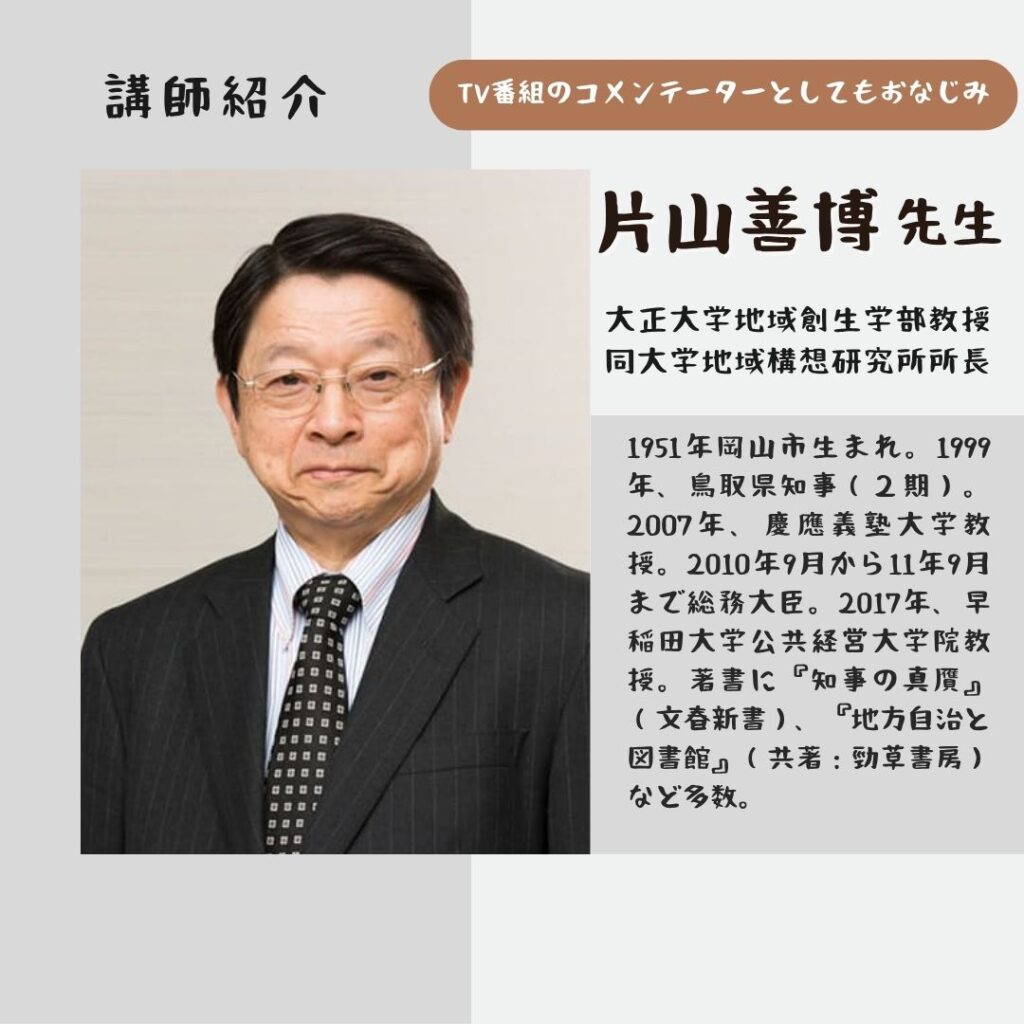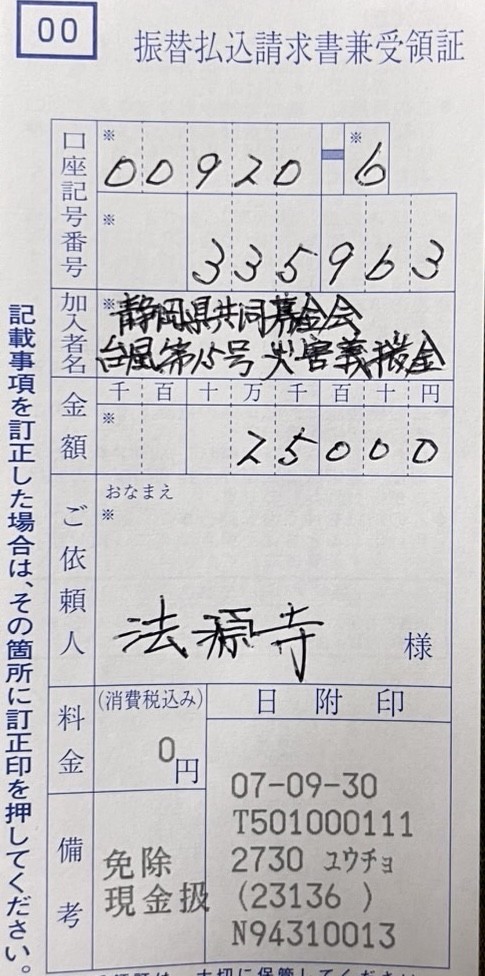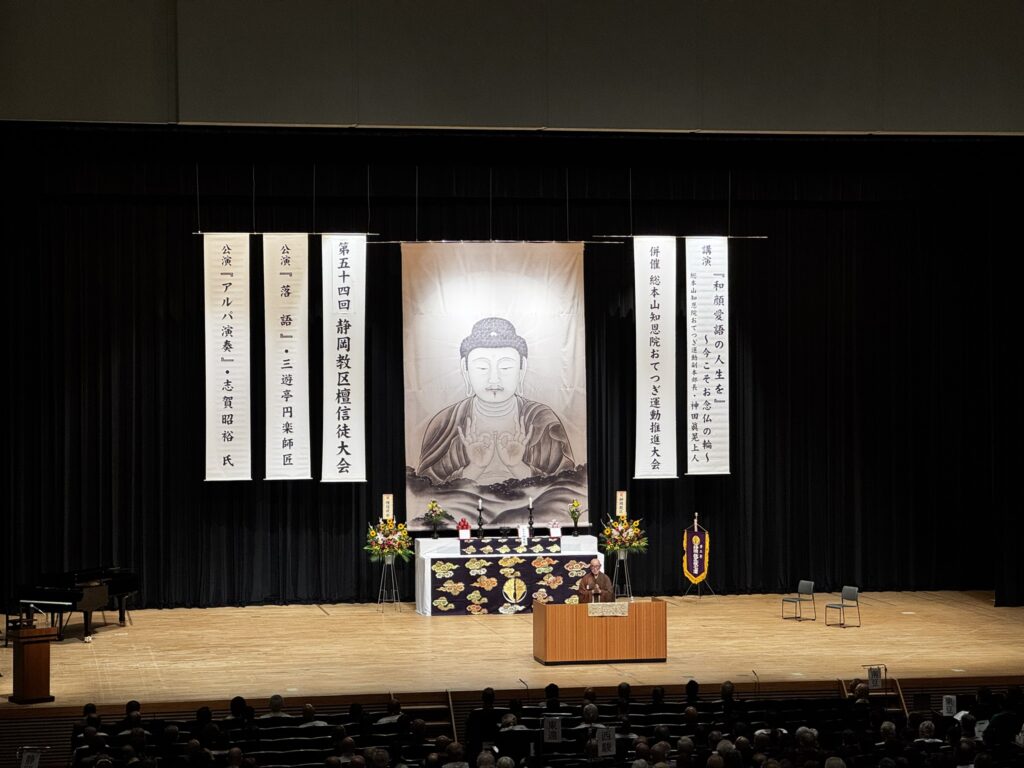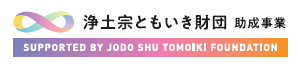先日、農園部の活動を行いました。
作業後、いつものようにグループLINEのアルバム機能で写真を保存しようとしたら「これ以上アルバムを作成できません」との表示が・・・
どうやらひとつのグループで作成できるのは100件までだそうです。ということは、この日は101回目の活動ということになります。
2021年3月上旬にジャガイモを植え付けてから足掛け6年。細々ではありますが、長く続いてきました。
もとは飛び地境内の整備から始まったこの活動ですが、富士市若者相談窓口ココ☆カラとつながる若者たちの居場所、社会参加の場所として、ずいぶん定着してきたように思います。農園活動が始まった時からずっと継続して手伝いに来てくれている若者もいますし、1年前から参加し、ほぼ毎回来てくれる若者もいます。
収穫の際には近隣の檀信徒のお子さんたちも参加し、年々にぎやかになってきました。

多くの人とのご縁を耕す場所になるよう、これからも続けてまいりたいと思います。
今度とも応援のほど、よろしくお願いします。













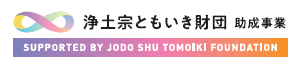
-1920x1200.jpg)
-807x1024.jpg)