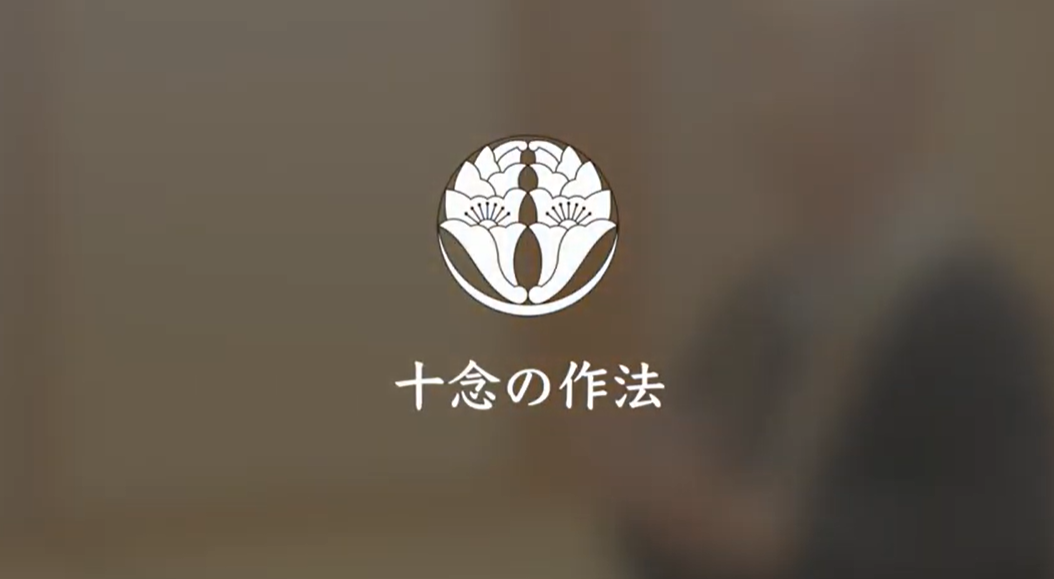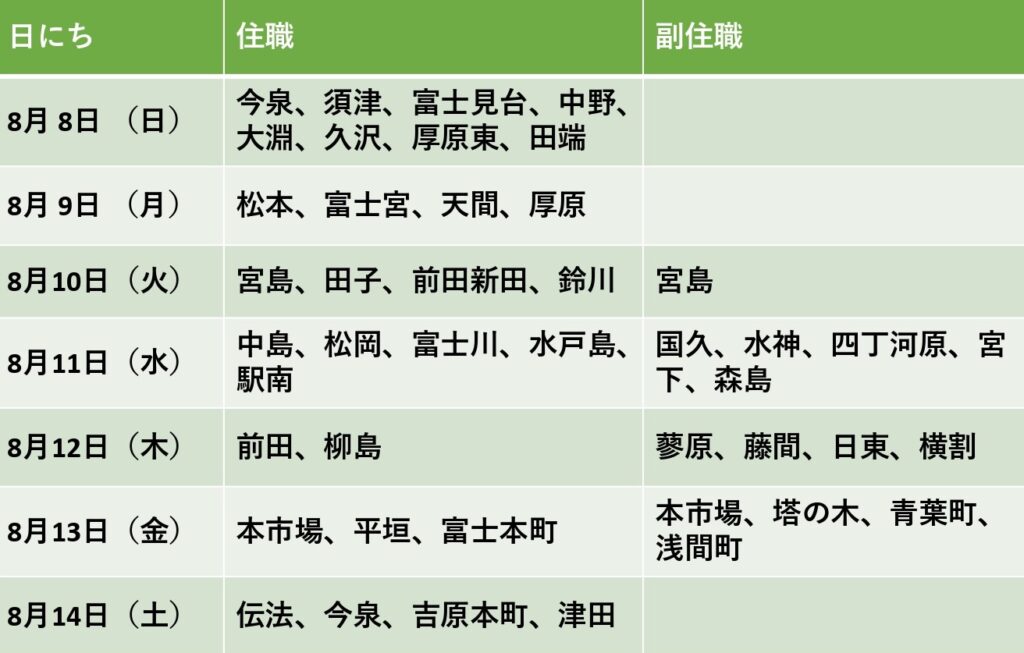11月3日は文化の日です。博物館や美術館の中には入館料を無料にしたり、様々な催し物を開催したりする所もあり、文化に親しむ日とされています。
みなさんは、「文化」というとどういうものを思い浮かべるでしょうか?
本日、皇居では、文化勲章の授章式が行われます。今年の受章者には、歌舞伎俳優の尾上菊五郎さんや元・読売巨人軍の選手で監督も務めた長嶋茂雄さんらがおり、そのほかには学術の世界で活躍された方々などがいらっしゃいます。昨年は脚本家の橋田寿賀子さんも受章しました。文化というと、こういった伝統芸能やスポーツ、芸術の中にあると感じられる方も多いのかもしれません。しかし、私たち日常の営みこそ「文化」があるのではないかと感じるのです。
大正時代に、柳宗悦(やなぎむねよし)という思想家が、民藝(みんげい)運動を始めました。
当時、工芸品は華美な装飾を施した観賞用の作品が主流で、これらを美術的価値があるものとして評価する風潮がありました。しかし、柳宗悦は、名も無き職人の手から生み出された日常の生活道具を「民衆的工芸(=民藝)」と名付け、日常生活の中にこそ美があると唱えました。使われるために作られたものの中にこそ、魂が宿っている。人々の生活に根ざした「民藝」には機能的な美しさがある。と、新たな「美の価値観」を提示したのです。
このことからすると、私たちの身近にあり、普段は気づかないけれど、当たり前のように行われていることにも、私たちの思いや感情が込められた「文化」があるのではないでしょうか。たとえば、神仏に手を合わせる。お墓参りをする。先祖を供養する。芸術鑑賞や楽器演奏とは違いますが、これもまた私たちの体に血肉化された「文化」です。
日本に仏教が伝わって1500年、浄土宗が開かれて850年の年月が流れています。その間、仏教は形を変えながら、私達の日々の生活の中に深く根差してきました。
先祖供養もそのひとつと言えます。この連綿と受け継がれてきた、教えと実践を、受け止め、次世代に伝えていく。これもまた文化を継承していくことと言えるでしょう。
年回法要を務めることは、亡き方のご供養になることはもちろんですが、私達、現世にいるものにとっても次世代への文化を伝える重要な意味があると思っています。
一方で、東京をはじめとした首都圏では、コロナ禍により仏事が省略されることが多いと伺います。
目に見えがたい精神文化をどう形に残していくのか、どのような文化を残したいのかが、今問われているように思います。手を合せ、十遍のお念仏を唱える。法然上人以来受け継がれてきたこの文化を、寺院として広く世に伝えていきたいと思います。
南無阿弥陀仏